契約書を締結できないときの対処法
.jpg)
ビジネスでトラブルを防ぐために、取引先との合意事項については契約書を交わすことが重要なのは言うまでもありません。ただ、時間が取れない場合や、相手が契約書の締結を渋る場合などもあると思います。正式な契約書を締結するまでの過程で合意した事項を都度確認しておきたい場合もあるでしょう。
このような場合はどうしたらいいのでしょうか。
1.口頭での合意を記録に残しましょう
.jpg)
保証契約などのいくつかの例外を除けば、口頭でも契約は成立します。ただ、口頭での合意では、後にトラブルになった場合に主張を立証する証拠が残りません。そのような場合には、以下の方法で法的に有効な証拠を残すことができます。
①議事録
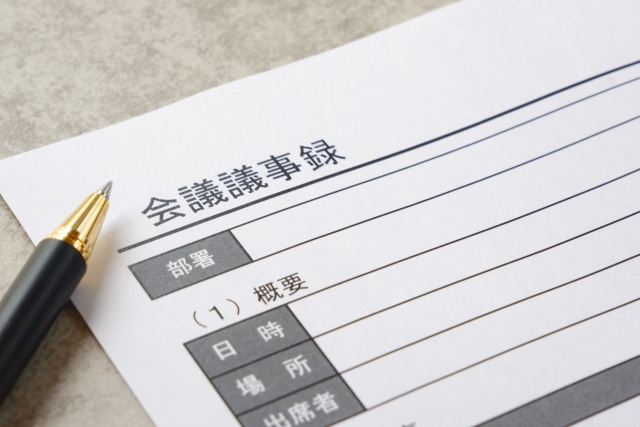
会議や打ち合わせを行った際に作成する議事録も契約書の代わりになります。この場合、署名や印鑑などで当事者が合意したことを示す証拠を残すようにします。電子メールでやり取りを行い議事録中に署名等を残すことが困難な場合には、内容に合意したことがわかるメールを残すようにします。
②電子メール

電子メールの記録も、当事者の合意があれば契約書の代わりになります。議事録と同様、一方的に送って終わりにするのではなく、相手が合意したことがわかるような記録を残すようにします。メールは定まった形式がなく多数のやり取りが交わされることが多いので、最終的な合意事項が明確になるようなものを残すようにします。
③注文書・請書

注文書や請書に商品種類、数量、価格といった取引条件に加え、保証や紛争解決方法など契約書で定める条件を記載しておき、取引にその条件が適用されることを明記します。ただし、この方法ですと、合意があったといえるかどうか疑義が生じる可能性があります。また、注文書と請書に互いに自分に有利な条件の書面を送りあうといった問題に発展する恐れもあります。注文書と請書のみで取引を続けることはリスクがありますので、基本契約を締結しておくことが望ましいといえます。
④録画・録音

ZOOMなどのオンラインミーティングの録画機能で記録を残す、スマートフォンやICレコーダーで録音するなどの方法があります。
2.注意点
ここで説明した方法は、口頭での約束という証拠の残らない合意の問題点を排除するためのものです。ただし、十分に内容を検討して作成する契約書に比べると、内容が曖昧であったり不十分なものになりがちです。取引の規模や重要性を考慮し、必要な場合は正式な契約書を結ぶようにしましょう。
3.相手が「契約書」という形式を拒むときは
「契約書」という固い名称の書面締結に難色を示す相手に対しても、上記の方法で何らかの記録を残すようにします。
また、同じ内容であってもタイトルを「覚書」「協議書」「打合せ記録」などに変更することで相手が受け入れてくれる場合があります。契約書のタイトルには法的な意味はなく、内容が同じであれば、タイトルにかかわらず同じ法的効果があります。
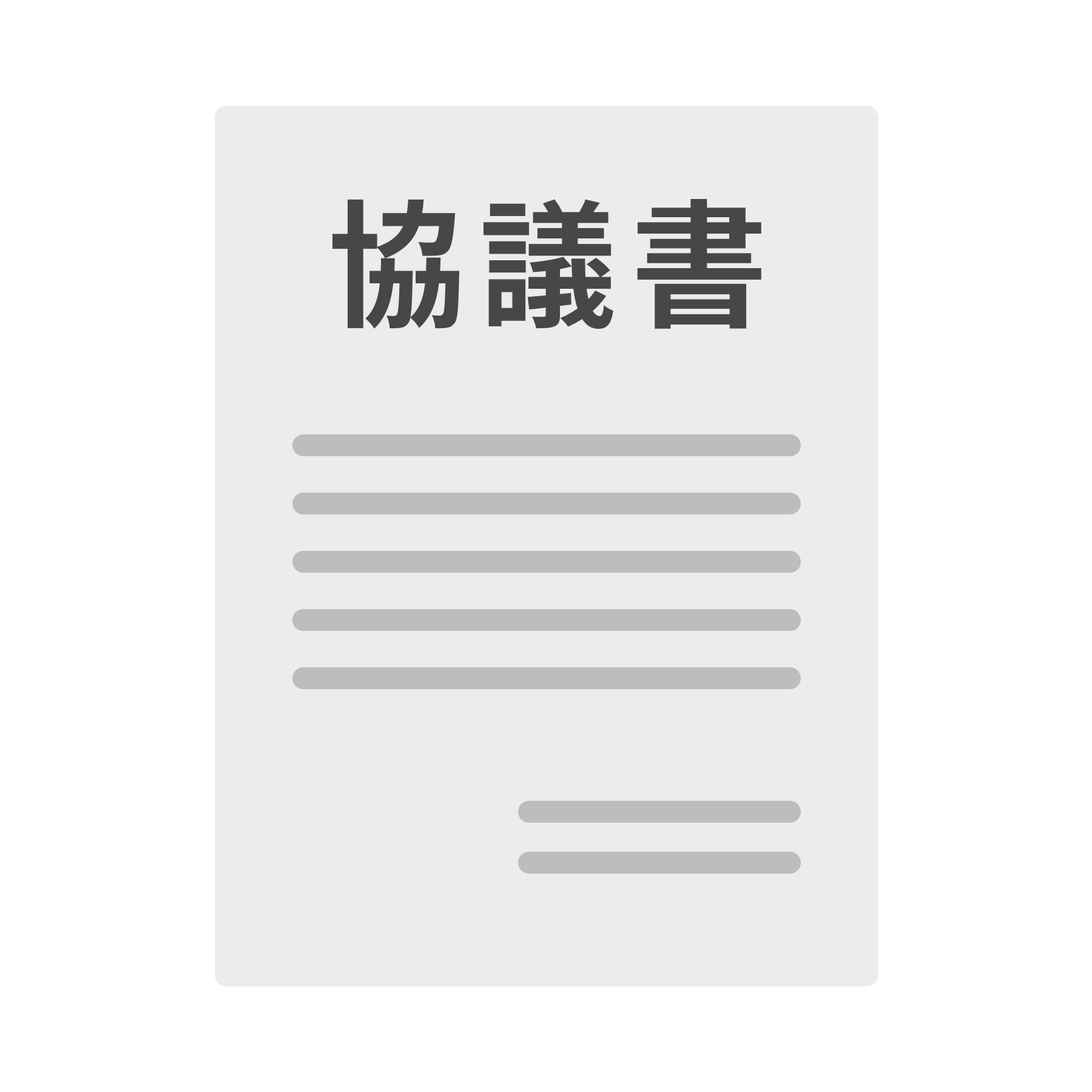
契約書のタイトルについては、こちらの記事も参考にしてください。
契約書様式のチェックポイント① ― 契約書のタイトルに惑わされないよう注意しましょう ―


