秘密保持契約書(NDA) ―情報の開示者・受領者それぞれの立場から見たチェックポイント―
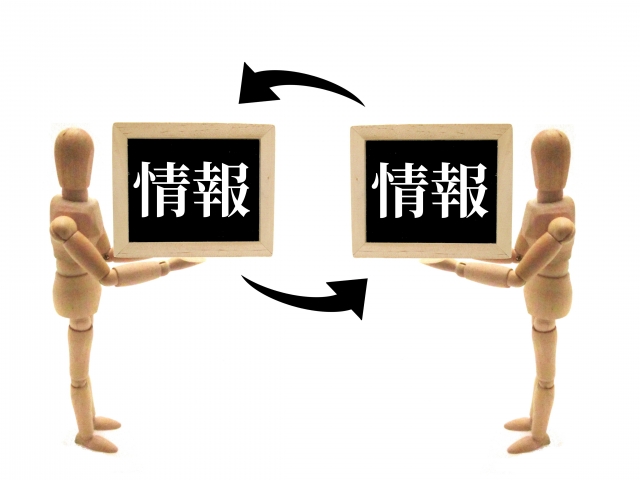
1.秘密保持契約書(NDA)とは
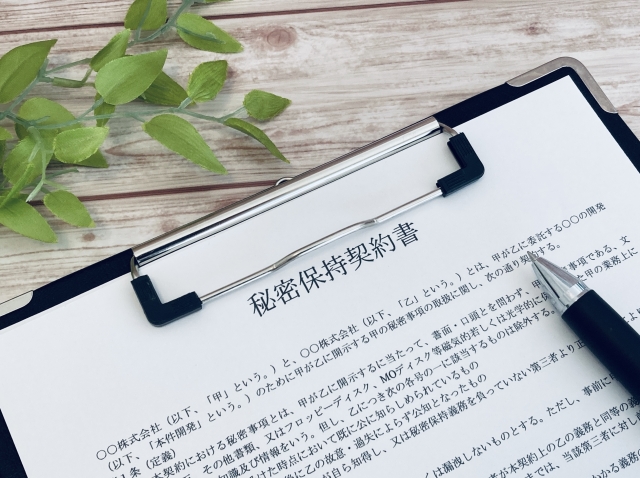
秘密保持契約とは、取引相手と相互に開示・受領する情報(秘密情報)の取扱いルールを定めるための契約書です。新規の取引先と取引を開始する段階で締結することが一般的です。英文の名称であるNDA(Non-Disclosure Agreement)もよく使用されます。
2.秘密保持契約書のチェックポイント

契約の当事者として、二つの立場があります。
① 主に秘密情報を開示する立場(以下、「開示者」といいます。)
② 主に秘密情報を受領する立場(以下、「受領者」といいます。)
例えば、A社が新たに開発した技術についてB社から問い合わせを受けた場合に、未公開の技術情報やサンプルを開示することがあります。このとき、情報やサンプルを提供するA社は①の開示者に、それらを受領するB社は②の受領者に該当します。
①②のどちらの立場になるかによって、好ましい契約条件が異なります。
開示者であるA社は、広範囲な情報を対象とし、厳格な守秘義務を課したいと考えるでしょう。一方、受領者であるB社は、情報の範囲を限定し、過度な制約を受ないようにしたいと考えるでしょう。
なお、B社が受け取ったサンプルの評価結果や想定顧客の情報をA社に提供する場合は、A社・B社とも重要な情報を開示・受領することになり、両者が開示者・受領者の役割を担うことになります。このような場合は、開示者の立場を基本としつつ、どちらの立場に近いかを考慮して契約条件を検討します。本稿では、それぞれの立場から見た契約書の主なチェックポイントについて解説します。
(1)目的
秘密情報をどのような目的に使用できるかを定めます。これは、契約の対象となる情報を特定し、目的外の使用を禁止する意図が含まれています。そのため、自社の認識と一致していることを確認することが重要です。以下、事例で解説します。
(例1)A社の〇〇技術に関する事業化の検討
(例2)A社の〇〇技術を用いた〇〇製品開発に関するB社との共同開発の可能性の検討
例1における「事業化」という用語は解釈の幅が広いため、受領者はほぼ制限なく情報を利用できます。一方で、例2のように使用目的を詳細に定めることで、情報の使用を「特定の製品分野におけるB社との共同開発の検討」に限定し、それ以外の使用を防ぐことができます。
なお、目的は独立した条項として設ける以外に、契約書の頭書(冒頭の導入部分)に「・・・について検討するにあたり秘密保持契約を締結する」などと記載されることもあります。
【開示者の立場でチェック】
自社の秘密情報を想定外の目的に使用されることを防ぐために、正確かつ限定された目的となっているか確認しましょう。曖昧な定義にすると広範囲に情報を使われるリスクがあります。また、目的外の使用禁止が定められているかを、忘れずに確認しましょう。
【受領者の立場でチェック】
目的を広範囲に設定することで、秘密情報の利用における自由度を高めることができます。一方で、過度に厳格な制限を設けると、意図しない目的外使用が発生する恐れがあるため注意が必要です。将来的に利用範囲が拡大する可能性も考慮して、目的を定めるようにしましょう。
(2)秘密情報の定義
秘密情報を定義する方法にはいくつかの選択肢がありますが、主に以下のいずれかの方法が取られます。
① 開示されたすべての情報を対象とする。
② 秘密である旨を特定した情報(「社外秘」「Confidential」などで特定した情報)を対象とする。
①の場合、開示者が秘密情報であることを個別に指定する必要はなく、口頭や映像による情報の開示についても特別な対応を要しません。一方、受領側は受け取った全ての情報を秘密情報として管理しなければならず、管理負担が大きくなります。
②の場合、開示者は、どの情報が秘密情報に該当するかを明示する必要があり、負担が生じます。一方で、受領者は秘密情報が明確であるため、管理が容易となります。口頭や映像による情報については、開示時に秘密情報であることを伝え、一定期間内に秘密である旨を文書で通知する方法が一般的です。
なお、①②のいずれの方法を採用する場合でも、口頭や映像による情報は形として残らないため、後から特定することが難しくなる場合があります。そのため、事前に対象を明確にし、不要な開示を避けるとともに、議事録などを作成して開示内容を記録・確認する対応が求められます。
【開示者の立場でチェック】
開示されたすべての情報を秘密情報に含めることで、漏れを防ぐことができます。そのため、①の「開示されたすべての情報を対象とする方法」が有利と言えます。
なお、②の「秘密である旨を特定した情報を対象とする方法」を採用せざるを得ない場合でも、重要な情報については制限を受けずに保護できないかを検討しましょう。例えば、「ただし、〇〇情報は、秘密である旨の特定の有無にかかわらず秘密情報とする」といった例外条件を設けることで、重要な情報を確実に保護することが可能です。
【受領者の立場でチェック】
秘密である旨を特定した情報のみを秘密情報とすることで、秘密保持義務の範囲を限定することが可能です。そのため、②の「秘密である旨を特定した情報」を対象とする方法が有利です。
(3)秘密保持
秘密保持については、秘密情報を適切に管理し第三者に開示しない旨を定めます。必要に応じて管理のレベル、管理体制、分析・解析の禁止、複製物の作成制限なども定めます。
【開示者の立場でチェック】
情報の管理レベルが、開示する情報の重要度に見合っているか確認します。
また、サンプルやソフトウエアを提供する場合は、分析、解析、リバースエンジニアリング等の禁止を条件に加える必要がないかも検討しましょう。
【受領者の立場でチェック】
管理体制に関しては、契約で定めた条件と実際の管理体制に齟齬が生じないよう、実現可能性を見極めながら条件を定めます。受領者の立場として、後日に自社の情報と混同が生じ、情報の漏洩や開示者から情報漏洩や目的外使用の主張をされないように、秘密情報の使用者や使用方法を管理しておくことも重要です。
(4)秘密情報を開示可能な範囲
秘密情報を開示可能な相手を限定した形で列挙します。通常、受領当事者の役員、従業員が対象ですが、これ以外に親会社、子会社、関連会社、弁護士、コンサルタントなど(以下、「関係会社等」といいます。)にも情報開示を可能とする場合があります。
【開示者の立場でチェック】
秘密情報を開示可能な相手を、必要最低限の範囲に限定するようにしましょう。社内であっても単に役員・社員とするのではなく、「秘密情報を契約書で定める使用目的のために知る必要のある自己の役員・社員」に限定します。
また、関係会社等が情報開示の対象となっている場合、自社の情報が開示されても問題がないかを確認しましょう。もし、開示を許可する場合は、次のように制限を設けることを検討してください。
① 具体的な会社名等を列挙する。
② 「議決権付き株式の過半数を直接または間接に保有する会社」など直接の管理下にある会社に限定する。
さらに、受領者に対して、開示者の秘密情報の開示を受ける役員、社員、関係会社等に守秘義務を負わせる責任があることを明確にする必要があります。
【受領者の立場でチェック】
自社の役員や従業員以外に秘密情報を開示する関係会社等がいる場合、開示先として契約書に明記されているかを必ず確認しましょう。
販売部門や製造部門を子会社化している場合、事業化の検討において子会社と連携する必要があると考えられます。また、子会社が契約当事者である場合、業務の遂行にあたり親会社への報告や了承が必要な場合があります。
【関係会社等が独立して秘密情報を受領する場合】
ここで説明する関係会社等への情報開示とは、受領者を介した間接的な情報開示を指します。例えば、A社の秘密情報を受領したB社が、それをB社の子会社へ開示するケースが該当します。
一方、関係会社等が単独で相手と情報を授受することが想定される場合は、それぞれを独立した契約当事者として扱うのが望ましいでしょう。上記のケースで、B社の子会社がA社と直接情報のやり取りを行うことが想定される場合は、A社、B社およびB社の子会社の三者で契約を締結する形が適切です。そのうえで、必要に応じてB社とB社の子会社間でも、A社の秘密情報を共有できる旨を定めておきます。
また、別の方法として、契約はA社とB社で結びますが、B社の子会社によるA社の秘密情報の受領をB社による情報の受領として扱う方法などもあります。
(5)秘密保持義務の存続期間
原則として、契約期間中は秘密保持義務が継続し、期間満了とともに終了します。ただし、契約期間は情報開示を行う取引期間を定めるものであるため、秘密保持義務については契約終了後も継続させることが一般的です。その期間は短い場合で1年から3年、長い場合で5年程度に設定されることが多いようですが、永久的な義務とすることもあります。
【開示者の立場でチェック】
開示者としては、秘密保持義務の存続期間が長い方が有利です。開示する情報の重要性や量を考慮し、十分な期間が確保されているかを確認しましょう。
【受領者の立場でチェック】
秘密保持義務の存続期間が長いと、情報管理の負担が大きく漏洩のリスクが高まります。適切な期間に限定する必要があるかを検討しましょう。
また、契約の有効期間満了まで秘密保持義務が継続する場合、契約当初に受領した秘密情報ほど、長期間にわたり義務が維持されることになります。さらに、契約が更新されると秘密保持義務も延長されるため、その影響を考慮する必要があります。そこで、秘密保持義務の期間を「秘密情報の受領時点から〇年間」と定めることで、契約期間に左右されず、一定期間後に義務を終了させる方法も有効です。
(6)知的財産権の定め
秘密保持契約で特許などの知的財産に関する定めを行う場合、以下の二つの内容が含まれることが多いです。
① 秘密情報の開示が、関連する知的財産の譲渡やライセンスに該当しないことの確認
② 相手方から受領した秘密情報に基づいてなされた知的財産権の帰属
【開示者の立場でチェック】
①は確認事項であり、特に問題はありません。
一方、②については、注意が必要です。通常、秘密保持契約段階での情報開示は評価等を目的としたものであり、新たな知的財産の発生が行われるようなレベルの使用までを許諾する意図はないはずです。そうであるにも関わらず、新たな知的財産の創作を許し、受領者に権利が発生するようなことなれば、会社にとって重要な財産の流出になりかねません。
また、特許をはじめとする産業財産権は公開されるのが原則です。そのため、権利化を許すと意図せず秘密情報が特許公報などを通じて秘密情報が公開されるリスクもあります。
秘密保持契約の段階では、目的の範囲で秘密情報を使用することに制限し、必要に応じて共同開発など次の段階で知的財産の扱いを定めるのがよいでしょう。
【受領者の立場でチェック】
①は確認事項であり、特に問題はありません。
一方、②については、権利の帰属が不利にならないよう注意が必要です。知的財産が開示者の情報に基づく場合、その帰属は開示者になるか、または受領者と共有となる条件が主張されることが想定されます。たとえ、権利の帰属を受領者側とすることが可能であっても、知的財産の出願や実施により開示者の秘密情報を開示することになるため、知的財産の扱いに制限が生じる可能性があります。
知的財産が生じる可能性を踏まえ、この段階で知的財産の取り扱いを定めるのか、それとも、共同開発など次の段階で取り決めるのかを検討しましょう。
(7)情報漏洩が生じた場合の対応
秘密情報の漏洩が発生またはその恐れが生じた場合に、受領者がどのような対応を行うべきか、また、開示者がどのような対応を受領者に請求できるかを定めます。具体的には、情報漏洩発生時の開示者への通知とその後の対応などを定めます。例えば、以下のような取り決めを行います。
第〇条
甲および乙は、秘密情報の漏えいまたはその疑いがあった場合は、直ちにその旨を相手方に報告し、相手方の指示に従って適切な措置をとるものとする。
【開示者の立場でチェック】
まず、情報漏洩時の対応に関する条項が契約書に記載されているかを確認します。内容については、受領者が(ア)漏洩が発生した場合だけでなく、その可能性が生じた場合も通知をする義務を負っているか、(イ)そのような事態が発生した際に開示者に「直ちに」通知することになっていか、(ウ)具体的な対応を開示者の指示に基づき行わせることができるかといった点を検討します。
【受領者の立場でチェック】
受領者がこの条項の受け入れを拒むことは難しいため、過大な負担を負う内容になっていないかを検討します。例えば、秘密情報漏洩の恐れが発生した場合にどのタイミングで開示者に通知するかは難しい問題ですので、実務上の対応は別として、契約上はできるだけ時間的予習をもって通知できるようにしておくことが好ましいといえます。また、対応については、開示者の一方的な指示ではなく両者で協議のうえ決定するなど、対応に幅を持たせることを検討します。
(8)契約日
契約書の締結日の定め方はいくつかのパターンがありますが、主に以下の二通りがあります。
① 頭書や条文で契約日を定める。
② 当事者の署名欄に日付を記載し、捺印又は署名した日を締結日とする。
【開示者の立場でチェック】
契約締結前に秘密情報を開示していないか確認しましょう。締結前に開示した場合、その情報は契約の対象外となり、受領者に秘密保持義務は発生しません。このような場合は、契約日とは別に「発効日」を定め、その日付を情報開示前に設定することで、契約締結前に開示した情報も契約の対象に含めるようにします。なお、締結日を実際の日より前にずらす「バックデート」という方法もありますが、契約の有効性に問題が生じる可能性があり、当事者間のトラブルにつながるため避けましょう。
契約の日付については、こちらの記事も参考にしてください。
契約書様式のチェックポイント② ― 締結日と発効日の違いに注意しましょう ―
(9)契約終了時の措置
契約終了時には、開示を受けた秘密情報をその複製物を含めて返却又は廃棄する義務を定めるのが一般的です。
【開示者の立場でチェック】
開示者の立場から、返却や廃棄の方法が問題ないかを確認しましょう。実際に返却を求める代わりに廃棄証明を提出させる方法もありますが、契約終了時に開示者が希望する方法を選択できるようにしておく方が安心でしょう。
【受領者の立場でチェック】
受領者の立場では、返却や廃棄への対応が可能かを確認し、必要に応じて情報管理体制を見直すことが求められます。近年、電子メールなどによる情報交換が主流となっていますが、この場合は物理的な返還が不可能です。そのため、情報管理責任者を定め、その責任者のもとで情報の廃棄証明を提出するなど、現実的かつ実行可能な契約条件を設定することが重要です。
3.実務上の注意点

(1)自分の秘密情報を守るには
ここでは、契約による秘密情報の保護について説明しました。しかし、一度情報を相手に渡してしまうと、どのように情報が扱われるかはを把握することはできません。契約で禁止しても、受領者が分析やリバースエンジニアリングを行うことで、重要なノウハウが漏洩する可能性があります。秘密情報を守るためには、開示相手の信頼性を慎重に見極めることが重要です。また、開示する情報の範囲をよく検討し、リスクを最小限に抑える工夫が求められます。
また、契約上で「社外秘」などの特定義務が明記されていない場合でも、開示する情報にはできるだけ特定を行うようにしましょう。これにより、受領者に秘密保持義務を意識させることができるだけでなく、万一紛争が発生した際に当該情報が秘密情報であることを証明しやすくなります。
(2)相手の秘密情報の漏洩を防ぐには
秘密情報の受領者は、適切な情報管理体制を構築する必要があります。秘密保持義務は数年間、場合によっては永久に継続するため、その間に組織変更や人事異動が発生する可能性があります。情報漏洩を防ぐには、契約締結時に情報管理の方法を関係者と共有し、その後も定期的に管理状況をチェックするなど、継続的な対策が求められます。
また、受け取った資料やサンプルの紛失を防ぐことはもちろん、外部発表や特許出願の際に相手の秘密情報を使用しないよう注意が必要です。資料やサンプルと違い、人の記憶に残る情報の管理は難しい面があります。そのため、社外発表や特許出願の内容に受領した秘密情報が含まれていないかを確認するためのチェック体制を整備することが重要です。
4.まとめ
秘密保持契約は定型的なものが多く、十分に内容を確認せずに締結されることも少なくありません。しかし、情報の開示者か受領者かによって、契約上の注意点は異なります。ここで示したポイントを意識することで、契約内容をより適切にチェックするようにしてください。
当事務所では、貴社の実情に合ったオーダーメードの秘密保持契約書の作成が可能です。海外取引先との間で結ぶ英文契約書にも対応しています。お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

-300x200.jpg)
