英文契約書の基礎知識④ ―準拠法と紛争解決条項―

英文(国際)契約ては重要な取り決めです。日本の当事者間で結ぶ国内契約の場合、特に取り決めがない限り日本の法律が準拠法となり、争いが生じれば日本の裁判所に判断を仰ぐことになります。しかし、異なる国の当事者間で結ぶ国際契約の場合はそうはいきません。将来発生し得る紛争を想定し、どの法律に基づいてどこで解決するのかを慎重に検討する必要があります。
1.準拠法とは

準拠法とは、契約書をどの国の法律に従って解釈するかを決める取り決めです。原則として、契約書に記載されている内容が法律に優先しますが、記載されていない事項や契約書の記載だけでは判断できない事項については、準拠法に基づいて判断されます。
一般的には、慣れ親しんだ自国の法律を準拠法にしたいと考えることが多いですが、自国の法律以外を選ぶことも選択肢の一つです。特に、自分たちに有利または不利にならない場合には、他国の法律を準拠法とすることも検討に値します。
ただし、いずれの場合でも準拠法は後述する紛争解決地とセットで決めるのが望ましいです。日本の裁判所にニューヨーク州法に基づく判断を求めることは可能ですが、日本の裁判官はニューヨーク州法の専門家ではないため、正確な判断ができるかは不明です。そのため、日本の裁判所を紛争解決手段とする場合は、日本法を準拠法とするのが望ましく、両者を分けて考えるのは現実的ではありません。
なお、契約で準拠法を定めても、強行法規や条約が優先されます。消費者保護法、労働法、環境法、独占禁止法、知的財産法などは準拠法に優先します。また、ウイーン売買条約※の締結国では、この条約の定めが準拠法に優先します(日本はウイーン売買条約締結国です)。
※ウイーン売買条約(CISG)は、1980年に国際連合が採択した国際的な商取引に関する統一規則を定めた条約で、契約の成立、売買の義務、契約違反時の救済措置などが規定されています。この条約は契約で適用を排除することが可能です。ウイーン売買条約が必ずしも日本企業に不利というわけではありませんが、判例が少なく結果が見通しにくいことから、契約で排除するのことが一般的です。
2.紛争解決条項(裁判管轄条項/仲裁条項)とは

契約に関して紛争が生じた場合、裁判、斡旋、調停、仲裁などの紛争解決手段のうち、どの方法を選択するかをあらかじめ定めておく条項を紛争解決条項といいます。裁判を選択する場合は、どの国の裁判所で解決するかを事前に当事者間で合意しておきます(裁判管轄条項)。また、裁判以外の手段としては、次項で説明する仲裁が選択されることが多く、この場合も、どの国のどの仲裁機関を利用するのかを当事者間で事前に定めておくことができます(仲裁条項)。
3.仲裁とは
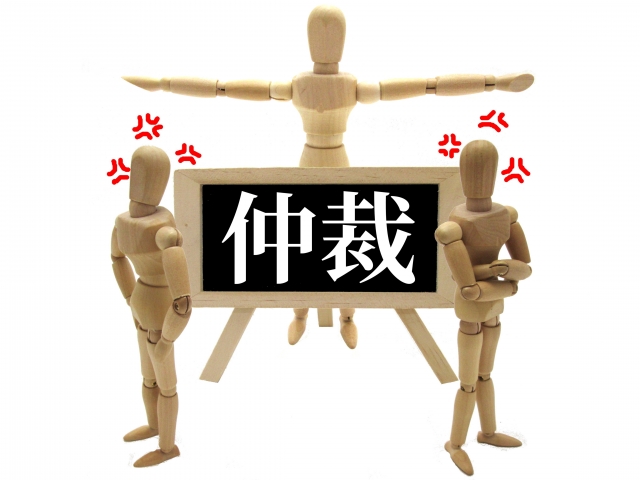
仲裁とは、国の機関である裁判所が行う裁判と異なり、第三者の専門家を仲裁人に選んで紛争解決を委ねる方法です。仲裁人の判断には裁判の判決と同様に法的拘束力があり、当事者が判断に従わない場合は、裁判同様に強制執行が可能です。裁判制度と比較した仲裁の特徴は以下のとおりです。
A)非公開で行われる(裁判は原則公開される)
B)当事者が選ぶ専門家が判断を行う
C) 一般に裁判に比べ手続きが迅速
D)ニューヨーク条約締結国では仲裁判断に基づき執行可能
E)1回の手続で結論が出る(裁判は三審制など複数回の手続が多い)
仲裁にはこのような特徴があり、次項で説明する執行上のメリットもあるため、近年多く採用されています。
4.判決または仲裁判断の執行

裁判であれ仲裁であれ、自分たちに有利な判断が出たとしても、相手が必ずしもその判断に従うとは限りません。重要なのは、判決や仲裁判断に基づいて相手の財産に対して執行できるかどうかです。
裁判や仲裁を行った国に相手の財産があれば執行は可能ですが、裁判の場合、異なる国にある財産に対して執行することは容易ではありません。A国での裁判の結果をB国でも認めてもらうためには、別途B国の裁判所に申し立てて承認をもらう必要があります。日本の裁判所で勝訴を勝ち取っても、それを外国の裁判所が承認してくれない場合もあるのです。
これに対して、仲裁にはニューヨーク条約と呼ばれる外国仲裁の判断の執行に関する条約があり、条約批准国であれば強制執行が可能です。この条約には日本を含む主要国が加盟しています。
5.第三国という選択肢

準拠法や紛争解決条項の決定において、契約当事者が互いに譲らず合意に至らない場合があります。このような場合の解決策の一つとして、紛争解決地に第三国を選択する方法があります。
よく利用されるのがシンガポールでの仲裁です。シンガポールは、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)を設立し、紛争を迅速かつ効果的に解決する場を提供しています。
6.紛争解決地・手段の選択基準

準拠法と紛争解決手段を検討する際の考え方の一例を示します。
A)準拠法は、紛争解決地とセットで考える
例えば、日本を紛争解決地とする場合は、日本法を準拠法にする方が手続がスムーズに進みます。
B)自国を紛争解決地とすると、手続き負担は小さくなるが、権利行使のハードルは高くなる
日本の当事者が日本で裁判・仲裁を行うことには、手続き負担が小さいというメリットがあります。また、相手にとって日本での手続きは負担となるため、相手から訴訟を提起されることに対する一定の抑止力が働きます。
しかし、相手の財産を押さえるためには、日本での裁判・仲裁判断を相手国の裁判所に承認してもらう必要があります。特に裁判の場合、そのハードルは高くなります。
C)相手国を紛争解決地とすると、手続負担は大きくなるが、権利行使にはメリットがある
日本の当事者が相手国で裁判・仲裁を行う場合、手続き負担は大きくなります。
しかし、相手の財産を押さえるためには、相手国で裁判・仲裁を行った方が手続が迅速かつ確実です。
D)合意を得るための解決策として第三国も選択肢
準拠法と紛争解決手段を第三国に設定することで、当事者間の平等が保たれ、合意が得やすくなります。シンガポールなどは、そのための制度が整っています。
E)一般論として、国によって手続が異なる裁判よりも仲裁の方が使いやすい
裁判は国によって独自の制度があり、また国によっては公平性に疑問が生じる場合があります。特に、ディスカバリー制度※、陪審員制度といった独特の制度のある米国での裁判は避けた方が賢明です。一方、仲裁は、当事者で仲裁人や手続ルールを選べるといったメリットがあります。
準拠法と紛争解決手段の選択は、手続きの負担を軽減したいのか、または相手に対する権利行使を確実に行いたいのかといった状況に応じて異なります。どの組み合わせが最適かは一概には言えませんので、英文契約の知識・経験がある専門家の意見を参考に判断することをお勧めします。
※ディスカバリー制度とは、米国で行われる民事訴訟において、訴訟当事者が相手方に対して、事件に関連するあらゆる証拠の開示を請求できる制度です。相手の情報を広範に取得することができますが、相手からの開示請求にも対応しなければならないため、手続の負担が大きくなります。


