契約書の修正に応じてもらえないときは

取引先によっては、自社の雛形契約書を提示し、その内容の修正に応じないケースがあります。通常、取引先の契約書は取引先に有利な条件で設定されているため、そのまま受け入れることが難しい場合も少なくありません。このような場合、相手の契約書を修正せずに受け入れるか、それとも取引そのものを見送るしかないのでしょうか。以下では、このような状況に対する対応方法を説明します。
1.対応方法
①修正できない理由を明確にしてもらう

修正に応じない合理的な説明が得られない場合、取引先の担当者が修正協議に応じるのを面倒だと感じている可能性があります。このような場合には、契約書のどの点がなぜ受け入れられないのか、自社として明確な理由を提示することが重要です。
相手に修正を拒む合理的な理由がない場合は、粘り強く交渉を続けることで、修正要求に応じてもらえる可能性があります。
②契約書とは別書面の修正契約を提案する
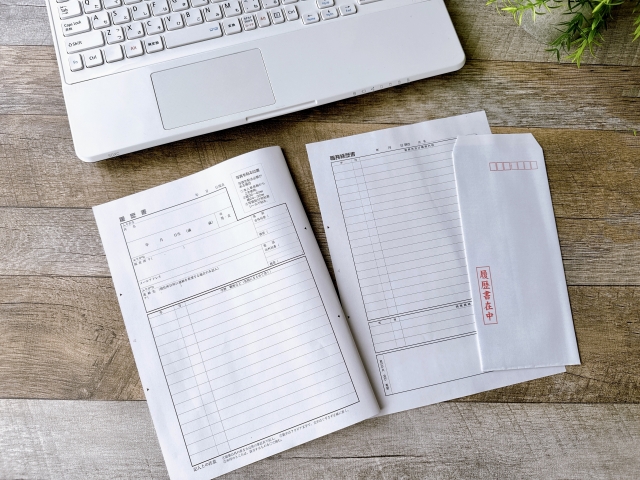
会社によっては、雛形契約書を修正する際に契約管理部門などの承認が必要となる場合があります。そのため、担当部門に決定権がなく、承認手続きに時間や手間がかかることを理由に、担当者が修正に消極的である可能性があります。
もっとも、こうした状況であっても、雛形契約書自体には手を加えず、別書面であれば担当部門の責任において修正が可能なケースがあります。
具体的には、修正契約書(修正覚書)を用いて、「〇〇契約書第〇条の取決めにかかわらず、△△については✕✕とする」といった形で修正します。この方法により、雛形契約書そのものを修正したのと同等の効果を得ることができます。
なお、契約書形式での合意が困難な場合には、議事録やメール等により合意内容を記録する方法もあります。
ただし、これらの方法を採用する場合には、雛形契約書に「修正の形式」や「修正に必要な権限者」についての定めがないかを事前に確認する必要があります。そのような条項が存在するにもかかわらず、それに反する方法で修正を行った場合には、当該修正は法的効力を有しませんので注意が必要です。
修正契約書や契約書形式以外の合意方法に関しては、こちらの記事も参考にしてください。
契約書の訂正・修正方法 ―訂正印や修正契約書などについて解説します―
契約書を締結できないときの対処法
③強行規定に違反していないかを確認する

契約は当事者の合意があれば自由に内容を決められますが、強行規定に違反する取決めは無効となります。契約内容が禁止法、下請法、フリーランス新法などの法律に違反している場合、そのことを根拠に修正を要請することができます。
強行規定に関しては、こちらの記事も参考にしてください。
契約と法律の適用順位
④サプライチェーン全体で契約のリスクを管理する

製品取引に関しては、自社のみで完結することは少ないと思います。そこで、契約の修正に応じてくれない取引先に製品を販売する場合に、部品の購入先や製造工程の一部を委託する外注との契約条件などを確認します。それを取引先から要請されている条件と比較して、同等あるいは大きな乖離がなければ、自社が負う責任の一部を外部に転嫁できているといえます※。その結果、自社が直接手がける部分の責任が大きくなければ、取引先提示の契約条件を受入れが可能と判断できるかもしれません。
また、市場で強い立場にある部品メーカーから部品を購入する場合に、相手の契約条件を受け入れざるを得ない状況の場合も、その部品を使った製品の販売先との契約条件を同等の内容にすることができれば、部品メーカーの契約条件を受け入れることが可能と判断できるかもしれません。
このように、一つの契約だけでなく、サプライチェーンで関連する契約全体でリスク管理を行う方法もあります。
※A ⇒ B ⇒ C といったサプライチェーンの中間に位置する事業者Bが、上流側(A ⇒ B )と 下流側(B ⇒ C )の2つの契約を締結する際に、その条件を同等にする契約をミラー契約などと呼びます。

2.口頭の約束には注意しましょう

取引先の担当者から、「契約書は修正できないが、私の考えではこの内容は〇〇なのでお互い意見の相違はない」などと口頭でコメントされた場合は注意が必要です。後にトラブルが発生した際に、口約束はほとんど役に立ちません。
3.まとめ
契約条件は当事者の力関係によって決まるため、取引先が優位な場合には契約交渉が難航することがあります。しかし、一度契約が締結されると、その後の取引は契約条件に従う必要があります。
取引を断念せざるを得ない場合もあるかもしれませんが、修正を拒む理由を把握すれば、それを回避するための具体的な対策を提案できる可能性があります。また、サプライチェーン全体を見渡し、契約リスクを管理する手法を併せて検討してみることも重要です。


-300x200.jpg)