継続的取引における段階ごとの契約手法 ―契約の種類とポイントについて―

商品の販売、サービスの提供、製造委託などでは、一回限りの取引だけでなく、長期にわたる継続的な取引を行うことが多いと思います。販売店や代理店となって継続的な取引を行うこともあります※。このような場合は、取引段階に応じて適切な契約書を取り交わす必要があります。
ここでは、モノやサービスの継続的取引で締結する契約書について、その種類、締結順序、知っておくべきポイントについて説明します。
※販売店と代理店の違いについては「2. 基本契約」参照。
1.秘密保持契約

取引の開始に先立ち、自社の情報やサンプルの提供などを行う場合、相手方に守秘義務を課すための契約を結ぶ必要があります。通常の売買取引では、秘密保持契約を締結することはあまりないかもしれません。しかし、継続的な取引を検討する場合は様々な情報を交換する可能性が高く、取引に至らない場合のリスクも考慮しなければなりません。そのため、交渉の初期段階で秘密保持契約を締結することを検討すべきです。
なお、秘密保持契約は、情報の開示に先立って締結することが原則です。契約の締結前に情報を開示しないよう注意しましょう。万が一、契約前に情報を開示してしまった場合は、契約の発効日を情報開示前に遡らせ、当該情報を守秘義務の対象に含める措置を講じる必要があります。
契約の発効日については、こちらの記事も参考にしてください。
契約書様式のチェックポイント② ― 締結日と発効日の違いに注意しましょう ―
【ポイント】
・情報を開示する(サンプルの提供なども含みます)のは秘密保持契約を結んでからにしましょう。
・契約締結が情報の開示後になった場合は、情報開示の時点まで遡って発効日を設定しましょう。
2.基本契約
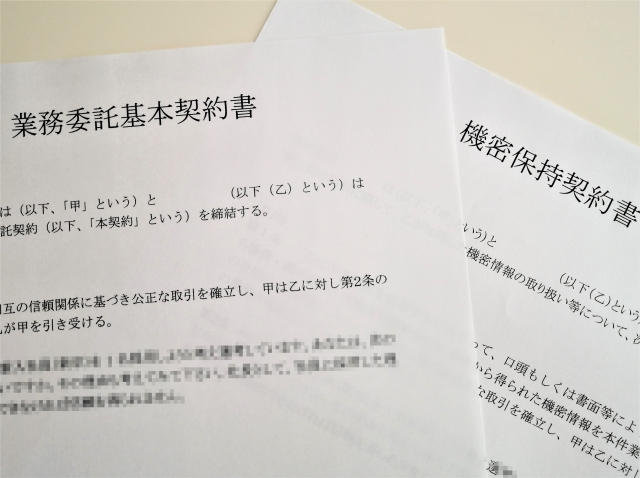
取引が長期にわたり継続する場合は、個々の取引に共通して適用される条件を基本契約で定めます。これにより、個別の取引では商品の種類、数量、価格など、取引ごとに変動する内容のみを定めればよく、効率化を図りながら取引の安定性を向上させることができます。
基本契約には、売買基本契約、製造委託基本契約、販売店契約、代理店契約などがあります。なお、販売店契約と代理店契約には以下のような違いがあります。
販売店契約
製品を製造・供給する企業(メーカーなど)が販売店に製品を供給し、販売店がその製品を自らの名義と責任で販売する契約です。販売店が製品の所有権を取得して顧客に販売するので、仕入価格と販売価格の差が販売店の利益になります。
代理店契約
メーカーやサービス提供者が、代理店に顧客への販売・提供のサポートを委託する契約です。製品・サービスの提供に関する契約は、メーカーやサービス提供者が直接顧客と結びます。代理店は、サポートの手数料(コミッション)が利益になります。
基本契約を締結すると長期にわたり影響を受けることになるので、将来を見据えた戦略が必要です。例えば、材料費や人件費の高騰で価格が維持できなくなる恐れがあるなど、将来的に契約条件の継続が困難になることが想定される場合は、条件の再交渉を義務化しておくことを検討しましょう※。
また、基本契約は、個別契約(「3. 個別契約」で説明)とセットで使用されるため、両者の間に齟齬があった場合に、どちらの条件が優先されるのかが問題になることがあります。優先順位を定めない場合は、後に合意される契約が優先されると解釈されますが、トラブルを避けるためには、基本契約で優先順位を定めておくとよいでしょう。
※価格等の契約条件変更は、状況によっては当事者の合意がなくても認められる場合がありますが、その適用範囲は限られています。そのため、将来的に条件変更の必要が生じる可能性がある場合には、あらかじめ交渉の機会を設ける条項を契約書に盛り込むことが望ましいでしょう。
【ポイント】
・基本契約は内容が多岐にわたるため、合意に時間を要します。早めに準備を開始しましょう。
・将来的に契約条件の継続が困難になることが想定される場合は、条件の再交渉を義務化しておくことを検討しましょう。
・基本契約と個別契約の内容が競合した場合に、どちらが優先適用されるのかを定めておきましょう。
3.個別契約
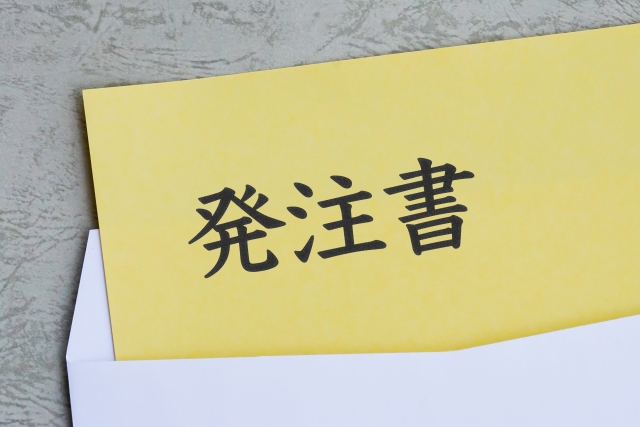
基本契約に基づき、具体的な取引内容を定める契約です。基本契約を定めておくことで、個別契約では品種、数量、価格、納期などの条件に絞ることができます。
発注書および発注請書も個別契約にあたります。なお、発注書を発行した時点では発注を行ったに過ぎず、個別契約が成立したわけではありません。個別契約が成立するのは、発注書と発注請書の双方が揃った時点です。ただし、基本契約で「発注書を受領してから〇日以内に承諾しない旨の意思表示をしないときは、個別契約は成立したものとみなす」といった取り決めがあれば、期限の到来により発注請書なしでも個別契約が成立します。
【ポイント】
・個別契約が基本契約で定められた条件(支払条件、解約条件など)と矛盾しないようにしましょう。
・発注書を使用する場合は、どの時点で契約が成立するかを基本契約で確認しておきましょう。
4.確認・修正に関する契約

契約は将来を見据えて条件を定めるものですが、後日に詳細が決まる場合や、状況の変化により見直しが必要になる場合があります。そのような場合には、当事者間で合意した内容を明確にするための契約を締結します。
具体例は、以下の通りです。
① 契約書作成時に詳細が未確定だった事項を、後日改めて定める。
② 契約内容に関する意見の相違が生じた際、当事者間で協議し合意した内容を明文化する。
③ 取引環境の変化に伴い、契約内容を修正(追加・変更・削除)する。
④ 契約の期間を延長・更新する。
いずれの場合でも、どの契約(原契約)のどの部分が対象になるのかを明確にしましょう。原契約は名称、契約日などで特定します。対象となる条文は、条文番号に加え、条文タイトルがある場合はそのタイトルも併せて明記しておくとよいでしょう。
契約を修正する場合は、修正により他の条文と矛盾することが無いように、契約書全体を見直すことも忘れないでください。また、修正は一度だけでなく複数回行われることがあります。同じ契約書に対して複数の修正がなされると、どれが最新のものかわかりにくくなります。そのため、「第〇回修正契約書」などのタイトルを付け、作成順序を明確にしておくとよいでしょう。
契約の修正と契約の延長・更新については、こちらの記事も参考にしてください。
契約書の訂正・修正方法 ―訂正印や修正契約書などについて解説します―
契約期間の延長・更新
【ポイント】
・契約の確認や修正を行う場合は、対象となる契約とその対象箇所を正確に特定しましょう。
・契約の修正を行う場合は、修正内容が他の条文と矛盾しないよう注意しましょう。
・複数回の修正が見込まれる場合は、タイトルに番号を付与するなどして、作成順序を明確にしましょう。
5.終了に関する契約

取引を終了する際には、必要に応じて契約終了のための合意書や確認書を交わします。
契約期間が定められている場合は、契約はその期限到来をもって終了します。一方、期間の定めがない契約は放置するといつまでも継続してしまうため、取引終了時に契約終了の合意書を締結し、契約関係が終了したことを明確にする必要があります※。
また、状況によっては、当初予定した期間満了前に契約を終了させたい場合もあります。その際、当事者が契約を終了することに合意した場合は、終了に関する契約を締結します。
終了に関する契約には、以下のような内容を記載します。
① 対象契約(付随する修正契約などがある場合はそれらも対象とする)
② 契約終了日
③ 契約終了の時点において未履行の義務や未払いの金銭などがある場合はその処理方法
④ 契約終了に伴い発生する損害や違約金がある場合はその具体的な条件
⑤ 守秘義務や競業避止義務などが残存する場合はその内容
なお、契約終了時点で債権債務等が存在しない場合も、その旨を確認する条項を定めておくことで後のトラブルを防ぐことができます。
中途解約条項や自動更新条項のある契約の場合は、通常、定められた期間内にいずれかの当事者が他の当事者に通知することで契約を終了させることができます。つまり、この場合は一方的な通知でよいのですが、債権債務の有無など確認しておくべき事項がある場合は、その内容を合意した契約を作成することも検討しましょう。
※製品の供給や販売店契約などの継続的な契約については、契約の終了をする場合に一定の制限が生じる場合があります。
【ポイント】
・終了に関する契約には、契約の終了日を具体的に記載しましょう。付随する契約がある場合は、それらも終了させることを忘れないようにしましょう。
・終了時点で、未履行の義務や未払いの金銭などがある場合は、その処理方法を明記しましょう。また、契約終了に伴い発生する損害や違約金がある場合は、その具体的な条件を記載しましょう。
・契約終了後も、秘密保持義務等が継続する場合は、その内容を記載しましょう。
6.まとめ
契約は一度確定すると、当事者を拘束します。そのため、将来起こり得る事態を十分に考慮し、慎重に条件を定めることが基本です。
一方で、継続的な取引では、当初予測できなかった状況に対応するため、条件の追加や変更が求められる場合があります。このような場合には、上述した段階的契約の手法を活用することで、リスクを軽減し、取引を円滑に進めることができます。
なお、契約内容を変更するには原則として相手方との合意が必要です。将来の条件見直しが想定される場合には、再交渉を義務付ける条項を契約書に盛り込むなど、長期的な視点に基づいた対策を検討しましょう。
当事務所では、契約書作成に関するご相談をお受けしています。
お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。


